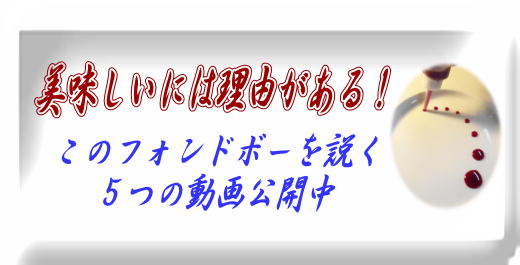- Home
- グルメな雑学, プロがすすめる道具編, 気になるお店, 食通の健康
- 食卓の安全を守る!まな板の清潔術と食中毒防止の徹底ガイド【ニイタカ サニクロールで安心を】
食卓の安全を守る!まな板の清潔術と食中毒防止の徹底ガイド【ニイタカ サニクロールで安心を】

毎日使うまな板、清潔にしていますか?
食中毒を未然に防ぐ安心のキッチン術
私たちの食卓を彩る美味しい料理。 食べるのは好きだけど、片付けやメンテナンスはしたくない・・・。
しかし美味しい料理の陰には、毎日のように活躍する大切な調理器具があります。
中でも、切る、刻む、たたくと、どんな料理にも欠かせないのが「まな板」です。
しかし、この身近な存在が、もし清潔に保たれていなければ、私たちの健康を脅かす食中毒の原因になりかねません。
今回は、そんなまな板をいつもピカピカに保ち、食中毒を未然に防ぐためのとっておきの方法を深掘りしていきましょう。
キッチンに立つ時間は、私にとって心安らぐひとときです。旬の食材を手に取り、どんな料理にしようかと考える。そ
の想像を形にする最初のステップが、まな板の上で食材と向き合う時間です。
鮮やかな野菜の色、新鮮な魚の輝き、そして肉の豊かな質感。
それらを丁寧に扱い、おいしさへと昇華させるための舞台がまな板なのです。
だからこそ、その舞台は常に清潔で、安心できる場所であってほしいと願っています。
食中毒の原因となる菌は、私たちの目には見えません。
しかし、温かくて栄養のある場所を好み、瞬く間に増殖していきます。
特に、生肉や生魚を扱った後のまな板は、まさに菌にとっての楽園。
そこで、まず実践していただきたいのが、まな板の「使い分け」です。
まな板の使い分けで食中毒を防止
料理のプロフェッショナルが包丁を使い分けるように、まな板もその用途に応じて
複数枚持つことを強くおすすめします。最低でも2枚、理想を言えば3枚あると、より安心です。
まず、「これから加熱する食材用」のまな板。これは、生肉や生魚といった、後で加熱調理する食材専用にしましょう。
これらの食材には、カンピロバクターやサルモネラ菌など、食中毒菌が付着している可能性があります。
別のまな板で切ることで、菌の交差汚染を防ぐことができます。
次に、「調理済食品用」のまな板。これは、サラダ用の生野菜や、すでに火を通したローストビーフ、パンなどを切るときに使います。
加熱済みの食品は、菌が死滅しているため、生のものとは分けて扱うことが食中毒の防止方法として非常に重要です。
もし、さらに余裕があれば、「野菜専用」のまな板を用意するのも良いでしょう。
土がついたままの野菜や、泥付きのゴボウなどを切る際に、他の食材への影響を気にせずに使えます。
このようにまな板を使い分けることで、食中毒菌が他の食品に付着するのを劇的に防ぐ効果があります。
まな板を清潔に保つ効果的なお手入れ方法
まな板を使い分けたら、次はそのお手入れです。素材によってお手入れ方法が異なりますので、ご自身のまな板の素材に合わせて実践してみてください。
木のまな板のお手入れ
木のまな板のお手入れ
木のまな板は、そのやさしい肌触りと包丁当たりの良さから、愛用している方も多いことでしょう。
使う前に水でぬらすことで、食材の匂いやシミが付きにくくなるというメリットがあります。
しかし、表面に傷がつきやすく、その傷の中に菌が潜んでしまうことも。
また、漂白剤を使用すると、木材が黒ずんでしまうことがありますので注意が必要です。
木のまな板におすすめなのは、熱湯消毒です。使用後、まずはたわしと洗剤で汚れをしっかり洗い流します。
その後、まな板をシンクに置き、沸騰したお湯をゆっくりと全体にかけましょう。
この時、やけどにはくれぐれも注意してくださいね。熱湯をかけることで、まな板に残った食中毒菌を効果的に殺菌することができます。
熱湯消毒の後も、しっかりと乾燥させることがまな板の殺菌において非常に重要です。
樹脂製まな板のお手入れ
樹脂製まな板のお手入れ
軽くて扱いやすく、食洗機対応のものも多い樹脂製のまな板は、現代のキッチンで大活躍しています。
樹脂製のまな板は、塩素系の漂白剤を使った殺菌が非常に効果的です。
まず、まな板の汚れを洗剤でしっかり洗い流します。
次に、まな板の上にペーパータオルや布巾などをかぶせ、その上から塩素系の漂白剤を全体にかけます。
こうすることで、漂白剤がまな板全体に行き渡り、効果的に殺菌できます。
5分ほど放置したら、たっぷりの水で漂白剤を洗い流し、最後に洗剤でしっかりと洗いましょう。
漂白剤のパッケージに記載してある注意書きをよく読んで、使用量や放置時間を守ってくださいね。
食中毒対策の基本は乾燥と保管
食中毒対策の基本は乾燥と保管
どんなに丁寧に洗って殺菌しても、その後の保管方法を誤れば、せっかくの努力が水の泡になってしまいます。
特に夏場は、湿度と温度が高いため、まな板についた雑菌が増殖しやすい環境です。
洗った後のまな板は、風通しの良いところで保管するなどして、乾燥させることを何よりも意識してください。
フックに吊るしたり、まな板スタンドを使ったりして、空気の流れを確保することが大切です。
完全に乾燥する前にしまうと、残った水分が菌の増殖を促してしまいます。
シンクの横に立てかけておく場合も、水が溜まらないように工夫し、定期的にシンク周りも清潔に保つようにしましょう。

食中毒防止のためのさらに一歩進んだ知識
食中毒防止のためのさらに一歩進んだ知識
まな板の衛生管理だけでなく、キッチン全体で意識したい食中毒防止のポイントは他にもあります。
調理器具全般の衛生管理
調理器具全般の衛生管理
包丁やボウル、ざるなど、食材に触れる調理器具はすべて、まな板と同様に洗浄と殺菌を徹底しましょう。
特に、生肉や生魚を扱った後の調理器具は、他の食品に触れる前に必ず洗剤で洗い、熱湯消毒や漂白剤での殺菌を行うことが大切です。
手洗いの徹底
手洗いの徹底
どんなに調理器具を清潔にしても、私たちの手が汚れていては意味がありません。
食材に触れる前、生肉や生魚を扱った後、トイレに行った後など、こまめな手洗いを習慣にしましょう。
石鹸を使って指の間や爪の先まで丁寧に洗い、清潔なタオルやペーパータオルで拭き取ることが食中毒の防止方法の基本中の基本です。
食材の適切な管理
食材の適切な管理
食中毒の原因は、食材そのものに付着している菌の場合もあります。
生肉や生魚は購入後すぐに冷蔵庫に入れ、他の食品と触れないように密閉容器に入れるか、袋に入れるなどして保管しましょう。
冷蔵庫の詰め込みすぎは、庫内の温度上昇を招き、菌の増殖を助けてしまう可能性があるので注意が必要です。
また、消費期限や賞味期限を常に確認し、期限内の食材を使用することが大切です。
中心までしっかり加熱
ほとんどの食中毒菌は、加熱によって死滅します。特に肉や魚、卵などは、中心部までしっかりと火が通っているかを確認しましょう。
目安としては、75℃で1分以上の加熱が推奨されています。
見た目だけでなく、竹串などを刺して透明な汁が出てくるか、色が変わっているかなどを確認すると安心です。
徹底的な殺菌にはプロの力も借りて
徹底的な殺菌にはプロの力も借りて
毎日の丁寧なケアに加えて、徹底的な殺菌を求めるなら、プロ仕様の殺菌料を取り入れるのも賢い選択です。
そこで、皆さんにぜひおすすめしたいのが、ニイタカ サニクロール 5.5Kです。
これはプロの厨房でも必須のアイテムです。我々も長年、お世話になっています。
この商品は、レビューの評価も人気も非常に良い業務用塩素系漂白剤です。
食中毒菌の殺菌に非常に高い効果を発揮し、まな板だけでなく、ふきんや食器、野菜・果物の殺菌にも使用できます。
食品添加物として認められているので、食品が触れる場所にも安心して使えます。
ただし、使用する際は必ず希釈して使い、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
特に、酸性の洗剤と混ぜると有毒ガスが発生する危険がありますので、絶対に混ざらないように細心の注意を払ってください。
ニイタカ サニクロール 5.5Kを定期的に使用することで、
ご家庭のキッチンをより一層清潔に保ち、食中毒の防止に大きく貢献してくれることでしょう。
まとめ:安心な食卓は清潔なキッチンから
まとめ:安心な食卓は清潔なキッチンから
料理は、ただお腹を満たすだけでなく、家族の健康を守り、豊かな生活を築く大切な行為です。その根幹を支えるのが、清潔なキッチンであり、そして清潔なまな板です。
今回お伝えした「まな板の使い分け」「適切な洗浄と殺菌」「徹底的な乾燥と保管」、そして「手洗いや食材管理」といった食中毒防止対策は、どれも少しの意識と手間をかけるだけで、私たちの食卓をより安心で安全なものへと変えてくれます。
毎日の料理を、心から安心して楽しめるように。そして、大切な家族の健康を守るために。今日からできる一歩を、ぜひ踏み出してみてください。清潔なまな板から始まる、安心と笑顔の食卓が、皆様の元に訪れることを願っています。
野菜の農薬!食中毒菌!気になる方へ?
by ?mimi?

材料(4人分)
酢 / 大匙3
塩 / 小さじ1
米ぬか / 大匙1
レシピを考えた人のコメント
できれば除去したいですよね?発がん性のある農薬。野菜の肥料として使用される牛糞は牛の腸管内に常在する病原性大腸菌あり。
詳細を楽天レシピで見る→